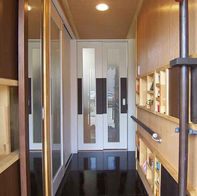New!!
(0307)
▼
New!!
(0307)
▼
New!!
(0307)
▼
New!!
(0307)
▼
New!!
(0307)
▼
New!!
(0307)
▼

Hironobu

TAKAHASHI

日本美
日本における「美」を表す言葉は、「クハシ(細(奈良時代)」、「キヨラ(清(平安時代)」、
「ウツクシ(細小(鎌倉時代))」、「キレイ(清潔(室町時代))」、と変化して来た。
日本人の美の意識は、清なるもの、潔なるもの、細かなものと同調する傾向が強い。
「かすか」なもの、「ほのか」なものに美を認めるのは、日本の伝統であったと言ってよい。
「ひたすらなもの」、「あらわなもの」は避けられた。
平安時代の宮廷で最も高い美の範疇の一つであった「なまめかし」。
その意味するところは、「十分の心づかいがされているが、しかも未熟のように見える。」
あるいは「さりげなく、何でもないように見える。」であった。
派手で、鮮やかな色や、紅葉の盛りのようなものは「なまめかし」とは言わなかった。
「なまめかし」が、最高の美の一つとして、貴(あて、高貴)と並んで重んじられているのは、
まさに今日いうところの日本的な美の感覚の一つが、この平安時代に確立されたということを
示すものと見てよい。
同じく平安時代に見られる「あはれ」という美意識は、四季の自然の移り行きに、こまやかな
情趣を感じる心であり、また男と女の愛情がはかなく移ってゆくのを悲しむ言葉であった。
千年にわたる日本人の美意識の中核として今日もなお生きている感覚と言えるが、
残念ながら言葉として、今日そのまま生きて使われているとはいえない。
本居宣長の説いた「もののあはれ」も、あらわな表現を避けて、洗礼された繊細さを重んじる美を指す
このように、古の日本人が持っていた、さりげない深い配慮を尊び、決して誇張しないという
奥ゆかしさの美を、今日の日本人は失いかけている。
日本の建築に見られる美意識も、この「さりげない深い配慮を尊び、決して誇張しないという
奥ゆかしさの美」を体現するものであり、この配慮は、形(かたち)となって表れている。
「形(かたち)」には意味があり、そこには作者の思いや配慮が込められている。
「形(かたち)」は、「心」の表れだ。


茶 室
空間を凝縮する。
この行為は、「空間の本質」を明確にすることに等しい。
「本質」で無い要素をきり棄てることである。
極限まで凝縮された空間は、たった二畳という狭さにもかかわらず、無限の広がりを見せ、そこでは濃密で深い親交が交わされる。
草庵茶室を完成させた千利休は、この凝縮された空間で、明日の命も覚束ない戦国武将たちと文字通り「一期一会」の時を過ごした。
現代人には想像もつかない、濃厚で重く、それでいて心安らかな時間を過ごす「空間」には、「本質」のみが求められた。
デザインの本質が「配慮」であるとする「眼」から見れば、このような茶室空間は、日本建築における「日本のデザイン」の極致であり、「日本美の象徴」と映る。
ここでの空間的要素は「配慮」という理念に貫かれ、「本質」を見い出すべく極限まで凝縮され、削ぎ落され、そして空間の「品格」を伴い昇華されていく。
泰平の江戸期や西洋化の嵐吹く明治期における我が国の先人たちは、このような茶室空間を見捨てず、継承してきた。
よくぞやってくれた。次は私たちの番だ。

現代_日本美の「かたち」と「心」

見立て
日本人の美意識として「見立て」という独特の感性が見られる。「見立て」とはある物の様子からそれとは別のものの様子を見て取ることを言う。
落語における扇子や手拭いが、様々な道具として表現されたり、茶の湯における千利休は、船の狭い入り口を転じて茶室の躙り口としたり、筒としての瓢箪や篭などを花入れとした。
このように「見立て」は、新たな視点、新たな価値観を生み出し、そこから多様で豊かな文化が生まれた。
先人たちに倣い、過去の日本建築の「かたち」や「心」を単に複写するといった「継承」ではなく、現代の日本人の視点や価値観、最新技術等で再構築し直し、新たな未来を「創造」し、次の世代に継承したい。



白銀比とは、およそ1: 1.414(5:7)の比率のことで 「大和比」とも呼ばれ、日本では古くから大工の間で「神の比率」とされてきた。
この白銀比は、いわゆる正方形における 各辺と対角線の比に等しい。
ある研究によると、日本人は西洋人が好むとされる黄金比(≒1:1.6)の四角形よりも、正方形を好む傾向があることが報告されている。


白銀比

連子とは、縦横に細い木を隙間を開けて組んだもの。格子とは区別される。
格子との違いは、格子が角材を縦横の格子状に組み上げた物を指すのに対し、連子は中間に補強用の水平材が入らずに、角材を縦方向だけに並べたもの。
連子は、見えそうで見えない控えめなデザインと言え、日本美の「さりげない深い配慮を尊び、決して誇張しないという奥ゆかしさの美」を示す形の一つと言える


連子(れんじ)

我が国は古より、大陸の文化や技術を積極的に導入し、日本という国を形成してきた。
ただ、導入されたもの・ことは、あらゆる分野において日本美の「さりげない深い配慮を尊び、決して誇張しないという奥ゆかしさの美」によって熟成され、昇華されたと言える。
一般的に言われる西欧美の特徴としての対称(シンメトリー)は、威厳や整然を表現し、我が国にも古くから導入され、受け入れて来た。しかし、私たち日本人はそれを更に昇華させ、「わざとずらし」非対称(アシンメトリー)とした。
「さりげない深い配慮を尊び、決して誇張しないという奥ゆかしさの美」


ずらし/非対称

日本人が持つ美意識としての余白とは、埋められなかった「余り(足し算)」では決してなく、 敢て「意図した空白(引き算)」とした「引き算の美学」がある。
「無作為の作為」
一見無作為に見えるが、実は非常に巧妙に奥深く作為されたもの。
自然に溶け込み、まるで人の手が加えられていないかのような日本庭園等では、計算し尽くされた日本人の美意識が隠されている。


余白・暗示

Architectural works






Architectural Design Competition

第10回医美同源デザインアワード
(2025.02)
立礼 待庵
入院患者はもちろん、そこに勤務する医療スタッフに
とっても、閉塞的で画一的な医療施設は、知らず知ら
ずのうちに精神的・肉体的ダメージを蓄積しやすい。
そこには、オアシス的空間と癒しの時間が必要だ。
この「立礼 待庵」は、ある意味厭世的な思考になり
がちな人々の聖域( サンクチュアリー) でもある。
安全上完全な個室化は困難だが、極限まで削ぎ落され
た極小空間に身を置くことで、我が国の茶室文化とそ
の歴史に培われてきた日本人の心を見つめ直す、静か
な時間が生み出される。
大切な人との気の置けるひと時や、孤を愛で、明日を
見つめる英気を養う、静謐で高貴な時間を演出する
空間を創造した。
C o n c e p t
侘茶を大成させた千利休は、わずか二畳の極小空間の茶室「待庵」を創造した。極限まで凝縮された空間は、たった二畳という狭さにもかかわらず、無限の広がりを見せ、そこでは濃密で深い親交が交わされた。
この「立礼 待庵」は、医療施設における車椅子利用を想定し、お見舞客などとの親密な時間を過ごすための最小限の機能だけを残し、最小限かつ濃密な空間を創造している。
三角に切り取られた和紙貼りの壁には、綿縄が連子状に吊るされ、緩やかに視線を遮り、中へ誘う。
内部空間は、車椅子の軌道等を考慮し、二畳より一回り大きな面積となったが、患者と訪問者との濃密で豊かな特別な時間を演出する。
貴人口、茶道口は客と主人との関係性により位置変換可能であるが、床(とこ)は固定され、床の背面には床窓の開口部があり、借景を可能としている。また点前にはさ
ながら炉にあたる喫茶(珈琲)用の電気ポット置場やカップ置場の最小限の機能性も有している。
ここで過ごす濃密な時間は、医療施設内での閉塞的気持ちを解きほぐし、静謐でやすらかな時間に代えてくれるはずだ。



宗像みあれ芸術祭 2024
(2024.06)
待庵
ここは、「神を迎い入れる場」である。
我が国には古より、喫茶により人と人とがより濃密な時間を過ごす「茶室」という空間が創造され、伝承されてきている。
この草庵茶室の究極のかたちとして、「侘び茶」を大成させた千利休の二畳の茶室が知られている。
この「待庵」は、その二畳の茶室を暗示させる台座(コンクリートブロック敷込み)に、神を迎える朱色の「貴賓口」を結界として、「みあれ(御生れ)」にて新たな力を得た神を迎い入れ、人と神との距離を縮める場となる。貴賓口正面には長さ2mの白木の柱を立て床柱とし、床には花器に一輪の草花を挿す。
神を迎えるこの茶室主人(人)の出入口の茶道口は、敷居のみが敷かれ、四方に壁もなく屋根もない。まさに暗示の空間であり、人を超越した神を迎える場にふさわしい。
神の拠り所となる御神木の前に白玉石を敷詰め清め、その中に創造された「待庵」は、周りの樹々や風、光を邪魔することなく、人と神とが出会う場を創出する。
実際には我々人間が、白玉石にて清められた聖域に立ち入ることは禁忌と考えられるため、立ち入ることは叶わないが、10月の大祭においては、まさに神が降り立つ天孫降臨の場となる。

さいかいタイニーハウスデザインコンテスト2023(2024.02)
LAT.33° N -「生きる」を問う-
北緯33°線上には、奇しくもイスラエルやアフガニスタン、シリア、イラクなど21世紀の現在でも紛争の絶えない地域へと繋がっている。
地球上で最後の原爆被爆地〈長崎〉から、この「LAT.33°N(北緯33°)」の意味を考え、平和のメッセージを世界に発信したい。
このタイニーハウスは、北緯33°を強く印象付けるコンクリートの壁上にあり、しかも北緯33°上の世界情勢の不安定さを暗示させる逆L字型(キャンティレバー)構造を採用している。そしてこの壁の真西の延長には、遠くの紛争地における平和を願うため、地球を模した石球が置かれ、北緯33°の意味を強く主張すると同時に、この地での平和の意味を考えさせる。
内部空間は、「食」「寝」「衛生」と名付けたの3つの最小限(ミニマル)空間から成り、それぞれを半屋外(通路部屋根あり)の坪庭が繋ぐ。約450年前、この地より中浦ジュリマンが天正遣欧使節団として「西」へ旅立ったその勇気を21世紀の我々が引き継ぎ、この地より世界平和のメッセージを発信し続けなければならない。
このタイニーハウスにて生活するということは、人間個人としての「生きる」ことの意味を問うと同時に、我々人類全体としての「生きる」すなわち人類の生存
を問う場でもある。
北緯33°線上のこの最小限の居住空間は、時間と空間を超え、未来を考える場でもある。



ミライREBORNスマイ プロジェクト(2023.08)
— 医・食・住 でミライの健康な都市生活 —
人間とは精神であり思考(考え方)である
2023年現在の未来予想は、概ね以上のようなことに集約される。
2050年、世界の人口は約 100 億人に達し、全人口の半数程度は100 歳を越える超高齢社会。社会はデジタル化した行政と巨大化したプラットフォーマーによって、中央集権的に管理・監視され、一方で経済合理性や効率性を追い求めすぎた結果、AI への過度な依存から脱せなくなり、創作活動や日々の意思決定までもAIに委ねてしまった・・・。
2019年、世界的パンデミックを引き起こしたCOVID-19は、仮想と現実の境界を見えなくした一方で、奇しくも仮想の限界と現実の重要性を示すものとなった。
仮想空間での行為や生活は、人間の精神(心)を置き去りにし、精神(心)を見失うことに繋がる。私たち人類は紛れもなくこの現実の世界で生きているのである。
2050年。我々人類はあらゆる分野で科学技術の恩恵を受け、何不自由のない生活を送っている。
各時代において危惧された私たち人類の「驕り」も、健全な自浄作用が必ず働き、回避できてきた。その拠り所となった場所こそが、この〈+Labyrinth(不迷宮)〉である。
世界的グローバル化によって、私たちは世界中の人々が、同じ服を着て同じ食べ物を食べ、同じような住宅で生活し、同じような価値観を共有しているように錯覚しているが、決してそうではない。
一見希薄になったように見える地域性や固有性は、皮肉にもグローバル化が進めば進むほど、心の奥底で疼きとなって現れ、己自身ののアイデンティティの模索を始め、その本質の深さに戸惑い慄く。
日本人の心に深く刻まれた、配慮を尊び、決して誇張しないという奥ゆかしい心は、「わびさび」「幽玄」「もののあわれ」「いき(粋)」「雅(みやび)」といった日本人独自の美意識を生み出した。
この目に見えないあいまいで不確実な美意識こそが、日本人の未来(ミライ)を幸福へと導く大切な理念とも言える。
人類20万年の歴史において、生息する地域は違えども、人類としてのDNAに刻まれし「互恵性」は、「人を人たらし得る証」である。
産業革命以降、物質的豊かさを希求した私たち人類は、人生の価値や幸福を、その数字の大きさだけで計ってきた。人類の歴史から見れば、ほんの一瞬の驕りを自省しなければならない。でなければ我々人類に2050年は訪れない。
2023年。残念ながら現在の未来予想では、「思想や哲学」に関する予測は見い出せない。
私たちは人間を信じている。


第7回 医美同源デザインアワード 出展(2022.02)
「壺中天」の意味は、安岡正篤氏の六中観(忙中閑あり。苦中楽あり。死中活あり。壷中天あり。意中人あり。腹中書あり)の一つ「壺中天あり」に由来します。
「壺中」とは別天地という意味で、人生の過程において、時には別天地で楽しむ時間も必要であるという意味を含み、まさに「医」に身を委ねなければをならない人々の心の拠り所となり、希望の明日へと導くような空間をイメージしています。
病み、傷つき、癒しが必要な人々の心と体を回復させる医療を行う「病院」という施設は、いわゆる医療を機能的・効率的に行うための空間でした。ただ近年大規模な病院等では、簡易的な商業施設や娯楽施設的空間が併設されたものも見受けられますが、人生を見直したり、人生の岐路に立つような体験をした者(患者)にとっては、これまでの「病院」は、決して「幸福な時間」を過ごせる空間ではなかったと考えます。
2016年の熊本地震は、最大震度7が2回観測された未曾有の大地震として、人々の記憶に刻まれました。私自身、被災者でもありましたが、地震発生後に放映されたあるテレビ番組にくぎ付けになりました。それは被災地の役場女性職員が、業務として遺体の搬送や避難所の運営に忙殺されながら日々を過ごしているというドキュメント番組でした。彼女はある日、医療サポートとして派遣されてきたケアチームの扉をたたき、医療スタッフにその心の内の葛藤や無力感をさらけ出し、一気にあふれ出す涙を止められない姿が映し出されていました。この女性職員は、自分自身も被災者でありながら、震災から約1か月間、ほとんど自分の身の回りのことは後回しにし、町役場へ訪れる被災者の対応に追われ、疲れ果て、いつ倒れてもおかしくない状況でした。しかしこの後、数週間経った頃、この女性職員に小さな変化が見られるようになりました。それが、ほんのりと彩られた唇の紅でした。大人の女性として日常、何の違和感もない「紅をさす」という行為が、一瞬で地獄絵図と化したふるさとの風景や止まった時間の中で、本人にとっても周りの人々にとっても大きな変化をもたらしました。私には、この「紅をさす」という彼女の美意識が、絶望に打ちひしがれていた彼女の心を未来へとつなぎ、確固たる負けない意志を表明したように見えたのです。テレビに映し出された女性職員のほのかな紅は、私にとって震災時や非常事態においても、美意識の重要性を確信させてくれた出来事でもあったのです。私はその時、あらためて人間としての生活を確立し、人としての心を保つためには、やはり「美」は必要だと強く思えた瞬間でした。
ここに提案する「空間」は、人間の人生にとって欠かすことのできない「美=芸術(創作)」を再認識する場であり、病み傷ついた心と体を癒し、明日への希望を見い出すような時間を過ごせる空間です。「工房」では、絵画や書道を創作し、「ギャラリー」では、創造された作品を鑑賞したり、周りの自然の中で四季の移ろいを感じたりし、「壺中天」では、まさに壺中に天があることを実感できる空間となっています。ある意味贅沢な空間ですが、「医美同源」を叶える空間と言える空間デザインであると考えます。


タイニーハウス デザインコンテスト (2021.08)
私( たち) のタイニーハウス
新型コロナウイルス禍に生み出された「新しい生活様式」は、苦肉の策であることは理解できるが、総毛立つ気色の悪さは拭えない。
ソーシャルディスタンスや三密回避といったキーワードに、明るい未来は決して描けない。人間は近接の動物だ。
視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感を通し、人は人を感じ、人を見抜き、人を信じ、共に触れ合い暮らしてきた。我々は新型コロナウイルス感染症対策として、一時的に触覚や味覚、嗅覚に制限をかけたが、人々の持つ違和感や嫌悪感は、近接の動物である証であろう。人は決して独りでは生きていけない。
このような理由から「2021 年のタイニーハウス」は、根本的意味が揺さぶられた。これまでの「集(社会)」から距離を取り「個孤)」を楽しむといった意味合いから、「集」での生活を拠り所とした「個」の確立を目指す人間本来の生き方を問う、新たな住空間の在り方の提案である。
ここでの「集」と「個」の関係性は、一見すると戦前まで見られた、長屋や団地での関係性と似ているように見えるが、過去、これほど「個」の多様性を認め、その重要性が主張された時代はない。かつては、「集」で生きることこそ、生命維持を約束するものであった。
しかし技術革新等によって、「個」での生命維持が可能となり、「個」は、多様性やオリジナリティを主張し、「集」を十字架や足かせと見做すようになった。だが新型コロナウイルス感染症によって、浮かび上がってきたものは、どれほど技術革新が進もうと、人は決して独りでは生きていけないという現実だった。人間はロボットや機械ではない。単にエネルギー補給のためだけの食事では、人は心を病んで、人間らしい生活を送れない。すなわち生命維持が危うくなるのだ。仲間や家族と楽しい会話をしながらでないと意味をなさない。現代に生きる我々は、この技術革新におぼれ、人間本来の生き方を見失い、礼儀やモラル、思想や哲学を疎んじ、効率のみを求めてきた。その象徴がまさに今日の「タイニーハウス」と言える。
ここに提案する「私のタイニーハウス」は「私たちのタイニーハウス」と言い換えられる。この提案は、「集(社会=村民)」に軸足を置いた、シンプルで小規模なミニマリズム的「個(孤)」の空間の確立であり、新たな住空間のフェーズを示すものと言える。小菅村の「村の木」として村内一円に広く植林されているヒノキ材を用いて、一辺2.4m の立方体グリッドで形成された構造体に、ミニマムな「個」の空間(タイニーハウス)を創出した。ただこれは、単なる「個」の極小住空間の提案ではなく、「共に生きる」ことを大前提とし、今日でいうシェアハウス的形態を取りつつ、隣接する別棟には、職住一体とも言える「工房(Lab)」を持つ。すなわち、「個」の確立には、生業をたて、社会( 集:村民) との接点の中で、生活を継続する必要がある。その依り代が、ここで提案する「タイニーハウス+工房(Lab)」だ。ここで想定される住人は、モノづくりや芸術・文化に関する興味を持ち、小菅村での21 世紀における「人間としての生き方」を実践し、情報発信する者とし、「アーティスト・イン・レジデンス」的機能も持つ。「タイニーハウス」の本質は、引き籠る空間ではなく、シンプルに人間らしく、共に生きる空間である。


第39回JAPANTEX2020
インテリアデザインコンペ2020 入選作品
「きよらの間 ―日本美の空間―」
新型コロナウイルス感染症の影響で、訪日外国人観光客は激減し、国内における県外への移動も憚られる昨今だが、ここ1~2年以内には、必ずやコロナ禍を脱却できるものと信じている。人間の歴史を振り返ると、我々人類は明らかに「近接の動物」であり、このままソーシャルディスタンスを保ったままの新たな生活様式を続けていたら、文化や芸術、人間関係や社会などは崩壊し、真の人間らしさを見失ってしまう。
そこで、2025年開催予定の大阪万博における人とつながるゲストハウスに対して、日本の底力を示す日本美の空間を提案したい。我が国における「インテリア」の初出は、平安時代の貴族の住宅様式としての「寝殿造り」とされ、基本的に間仕切りの無い空間で、障屏具によって空間を区画し、調度を配した。やがて室町時代の貴族の住宅「書院造り」になると、調度や障屏具などのインテリアは建築化され、障子や襖、付け書院や違い棚など、建築と一体化していく。
ここで提案する空間は、日本美の空間を代表する龍安寺石庭をモチーフに、砂利敷きに15個の石になぞらえたキャンドルを配した「石庭」、その両側には個(独り)の時間を楽しめる「方丈」を配した。入口から中央の「廊」正面には、着物の帯を掛け軸に見立て、お出迎えの空間としている。「廊」の左右には複数の客をもてなすための集(繋がり)の空間としての「座敷」と、軽食や飲み物を配した「厨(くりや)」がある。
「廊」「座敷」「厨」「石庭」「方丈」の空間は、〈すだれ〉によって柔らかく、しかも確かに区画され、拡がりと開放感を持ちつつ、落ち着いた空間を演出し、日本美の醍醐味を感じさせる空間を創造している。この作品タイトルの【きよら】とは、平安時代における最上級の美を表現する言葉であった。


ラブベンチデザインコンペ2019 出展
「お父さん座ろうよ!!」
このラブベンチは、菊池公園城山展望所から一望できる 菊池市の今を切り取る額縁となっている。
ベンチは、ハートのオブジェが造りこまれた「額縁」部と、格子状のスクリーンによって囲まれた『ベンチ』部からなる。ベンチに人が座っていなくても、眼下に広がる菊池市の風景を切り取る額縁として、来訪者の心を癒す。また更に、カップルが座ることで、このラブベンチは完結し、菊池の自然豊かな風景とカップルの後姿がまるで映画のワンシーンのように時間を切り取り、幸福な絵画を完成させる高齢化の進む地方都市の菊池市を一望できるこのラブベンチには、若いカップルというよりも、普段は手もつながなくなったカップルに座ってほしい
決して若くない者にとって、カップルで座るのは、気恥ずかしく、他人にはあまり見られたくないものである。そのためこのラブベンチは額縁に奥行きを持たせ、額縁の側面を格子状にし、見え隠れの効果を演出し、カップルの羞恥心を減らし安心感・包まれ感を増幅させている
このラブベンチは「おしどり夫婦の里」「妻を大切にするまち」をうたう菊池市民の男性たちにとって、まさに試金石の場であり、女性から「お父さん(パパ、あなた)、
座ろうよ」と言われたら断れない聖地であり、男性は必ず、日頃の感謝を「言葉にする」神聖な愛の空間となってほしい


ラブベンチデザインコンペ2018 出展
最初に菊池公園を訪れたのは、3月末。
園内の城山展望所も例年より早い、満開の桜に覆われていた。「桜」の花びらは、よく見るとハートのかたちをしている。桜を見ると幸せな気分になる所以であろう。
日本の国花は「桜」と「菊」であり、まさにこの菊池の地にふさわしい。ラブベンチの平面形状は、「菊」の形からインスピレーションを受け、直径φ1.2メートルの扇型としている。この形態は、着座時に自然と二人がやや向かい合うかたちとなり、膝が触れ合う角度となっており、また背もたれに囲い込まれた安心感が、二人の距離感に心地よさを演出している。
このベンチへのアプローチは、北側に接続された既設園路から行うが、北東に位置する記念碑の同心円状に“飛石”を配置した。それに誘われて奥へと歩を進めるとハート形の飛石に辿り着く。行き止まりの“ハートの飛石”で振り返ると、ベンチの縦のスリットにハートの形が浮かびあがる。(上部パース参照)このハートは、“ラブベンチの方位軸”でしか見出すことができず、このベンチがラブベンチたる所以の一つである。(北側園路からではわからない:立面参照)
“ラブベンチの方位軸”は、北から反時計回りに110度の角度に位置し、遠くに雲仙普賢岳を望み、冬至の日没方位とほぼ重なる。ベンチはこの方位軸を線対称とした、およそ240度の扇型をしている。基礎部はコンクリート製で、座面や背もたれは45ミリメートル角のチーク材に木部保護自然塗料を塗布し、メンテナンスや環境、人体への
影響を考慮している。また背もたれ小口部には、ポリカーボネート板を接着し、腐食防止対策を行っている。記念碑の陰になり、目立たないロケーションではあるが、ハートの背もたれに包まれ、同じ時間を共有したカップルは、きっと幸福な未来が待っている。